<就労継続支援B型事業所(お金編)⑬>生産活動と工賃の関係<~行政書士が解説~>
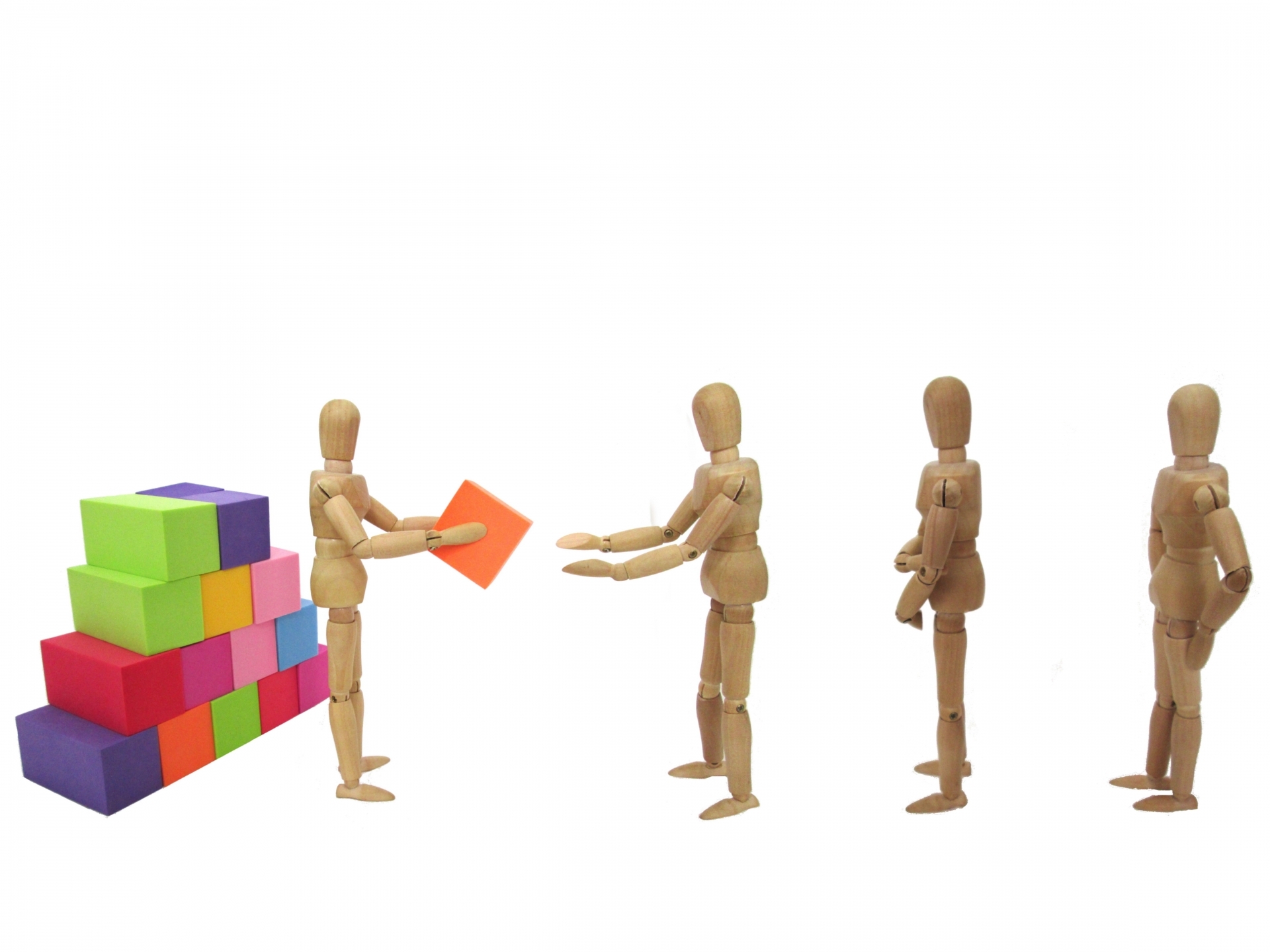
こんにちは、行政書士の大場です。
前回は、生産活動収入を“どうつくるか”という導入のステップをお話ししました。
前回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(お金に関すること)⑫>生産活動収入のつくり方<~行政書士が解説~>
今回はその次のテーマ・・・「生産活動で得たお金(売上)は、どのように工賃として利用者に還元されるのか」を整理していきます。
生産活動収入の構造
生産活動収入とは、事業所が“仕事”を通じて得た売上です。
ただし、そのまま工賃になるわけではありません。
実際には、次のような流れになります。
売上(生産活動収入)- 材料費(原価)- 経費(光熱費・人件費・備品など)
=
残り(利益部分)
↓
工賃として利用者に分配
つまり、生産活動収入は「売上」ではなく、“工賃を生み出すための原資”という位置づけです。
「工賃」とはなにか?
工賃とは、利用者さんが生産活動に参加した成果として受け取る報酬のことです。
法律上は「賃金」ではなく、“作業の成果に応じた分配金”として扱われます。
給与(雇用契約)ではなく、支援の一環としての報酬、したがって、最低賃金の適用はなく、分配方法は事業所ごとに異なります。
売上と工賃の関係
たとえば、ある月の売上が100万円の事業所があったとします。
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 売上(生産活動収入) | 印刷・販売などの収益 | 1,000,000円 |
| 材料費・経費 | 紙・包装・燃料・備品など | 600,000円 |
| 利益(分配原資) | - | 400,000円 |
| 利用者への工賃 | 月20人に平均2万円ずつ | 400,000円 |
つまり、利益部分がすべて工賃として還元されている状態です。
<注意>
「工賃を上げたい」と思っても、経費が増えれば工賃原資は減ります。逆に、原価を抑え、販売単価を上げれば工賃を伸ばすことができます。
工賃アップの基本式
工賃 = (売上 - 経費) ÷ 利用者数
このシンプルな数式に、B型事業所の“経営課題”がすべて詰まっています。
<行政書士の視点>
工賃アップは「経営」だけでなく「制度的努力」も関係します。たとえば「目標工賃達成指導員加算」など、報酬面の仕組みを活用すると、活動全体が安定します。
よくある誤解
→ 経費を引いた残りが工賃原資。経営管理が欠かせません。
→ 給付費は支援の報酬であり、工賃原資ではありません。
→ 量ではなく、単価と効率が重要です。
工賃アップの視点
| 視点 | 内容 | 行政書士のサポート例 |
|---|---|---|
| 経営 | 収益構造の見直し・原価管理 | 工賃アップ計画書の作成支援 |
| 制度 | 加算の活用・体制届の整備 | 目標工賃達成指導員加算などの届出 |
| 契約 | 取引契約書・覚書の整備 | 契約条件・納品トラブル防止 |
| 会計 | 工賃支払台帳・帳簿管理 | 実地指導での証拠整備 |
工賃アップは“数字の話”ではなく“信頼の話”
つまり、工賃は「事業の信頼度」を映す鏡ではないでしょうか
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(お金に関すること)⑭>生産活動収入の会計と書類整備<~行政書士が解説~>

