<就労継続支援B型事業所(お金編)⑫>生産活動収入のつくり方<~行政書士が解説~>
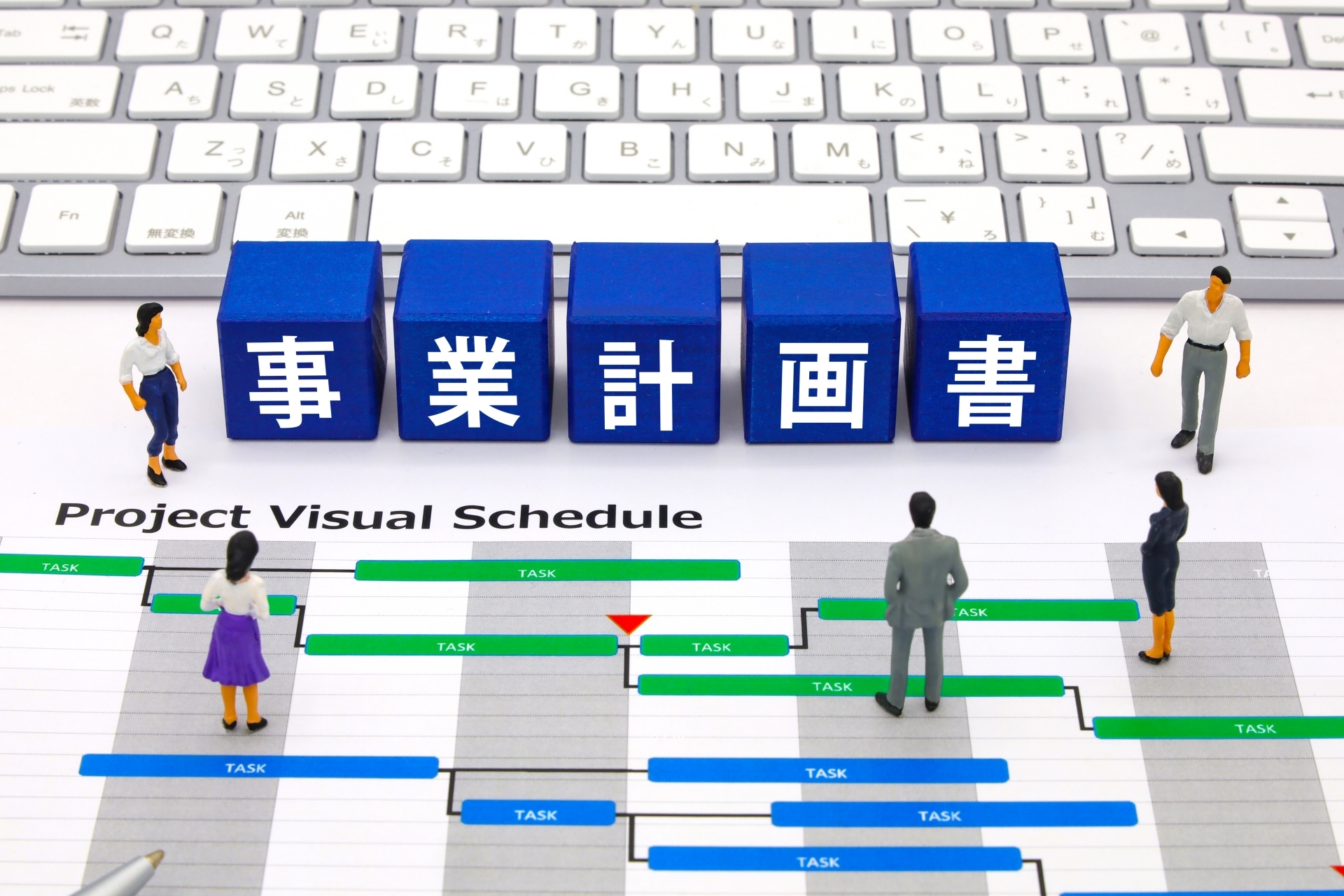
こんにちは、行政書士の大場です。
前回は、「生産活動収入とは何か?」をテーマに、給付費とは異なる“もうひとつの収入の柱”についてお話ししました。
前回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(お金に関すること)⑪>生産活動収入とは?<~行政書士が解説~>
今回はその続きとして、「どうやって生産活動収入を生み出していくのか?」実際の導入ステップと行政手続きのポイントを整理してみます。
スタートは「何をやるか」ではなく「なぜやるか」
最初の一歩で大切なのは、「なぜこの活動をやるのか」という目的づくりです。
<行政書士の視点>
目的が明確になると、「どの法令に関わるか」「どんな届出が必要か」が見えてきます。
代表的な生産活動の形
B型事業所でよく見られる生産活動を、分野別に整理すると次のようになります。
| 分野 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 印刷・デザイン | 名刺・封筒・パンフレットなど | 機械作業+デザイン要素、企業連携しやすい |
| 菓子・食品製造 | クッキー、パン、ジャムなど | 利用者参加度が高く、地域販売しやすい |
| 農業・園芸 | 野菜・花の栽培、農福連携 | 季節変動があるが地域連携効果大 |
| 内職・下請け | 梱包、組立、シール貼りなど | 初期投資が少なく、導入しやすい |
| 清掃・リサイクル | 公共施設清掃、古紙回収 | 安定受託につながりやすい |
導入のステップ
生産活動は、次の4段階で考えると整理しやすくなります。
| 段階 | 内容 | 行政書士が関われる部分 |
|---|---|---|
| ① 構想 | 目的・内容・必要設備を整理 | 事業計画書の作成支援 |
| ② 試作・テスト | 小規模に試して反応を見る | 取引契約書・覚書の整備 |
| ③ 販売・受託開始 | 販売・納品を実施 | 契約書・請求書・帳簿整備 |
| ④ 体制整備 | 工賃計算・記録管理・リスク対応 | 規程改定・手続届出・監査対策 |
< 行政書士の視点>
「いつ始めるか」より、「どの段階で届出が必要か」を見極めることが重要です。例えば、建物の用途変更や消防設備の追加は“販売開始前”に確認が必要になります。
法的手続きの注意点
生産活動は、福祉でありながら“事業”でもあります。
そのため、次のような法令や行政確認が関わります。
| 分野 | 主な手続き・確認項目 |
|---|---|
| 都市計画法 | 用途変更(例:作業室→店舗・製造室) |
| 建築基準法 | 建物構造・避難経路の確保 |
| 消防法 | 火気使用・製造設備の設置 |
| 食品衛生法 | 菓子・食品を扱う場合の営業許可 |
| 農地法 | 農地を利用する場合の転用・賃貸借 |
こうした手続きは、始めてからでは間に合わないこともありますので、事前に「構想段階」で確認することで、後のトラブルを防げます。

