<就労継続支援B型事業所(開設後手続き編)①>利用者契約とは何か?<~行政書士が解説~>
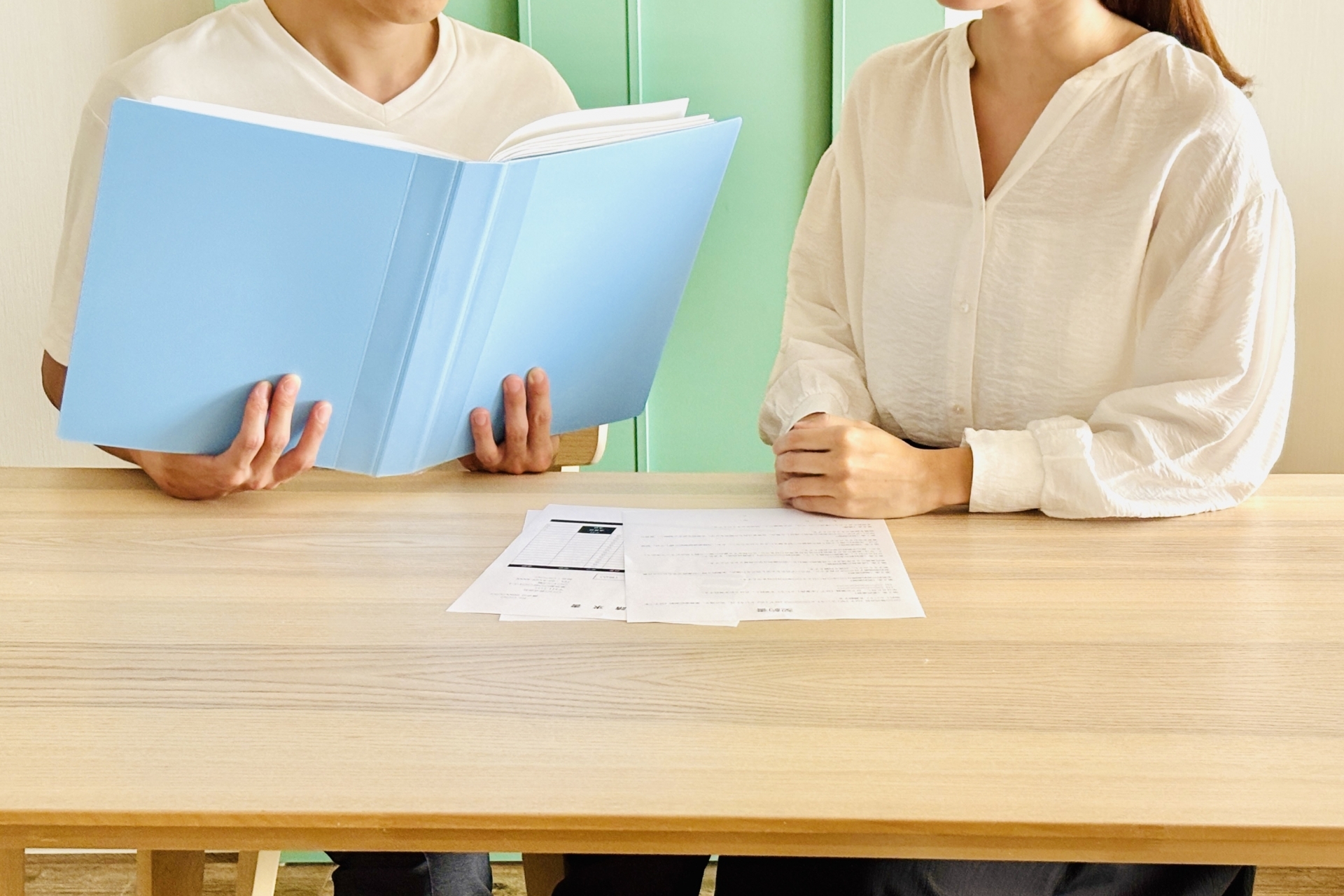
こんにちは,行政書士の大場です。
就労継続支援B型事業所を利用するには、まず「契約」というステップを踏む必要があります。
でも実際の現場では、「契約書はとりあえず印鑑をもらえばいいんですよね?」
「支給決定さえあれば、契約はあとからでも大丈夫ですか?」という声をよく耳にします。
しかし,この「契約」は、利用者の権利を守り、事業所をトラブルから守る“最初の約束”です。
今回は、その基本的な意味と位置づけを整理していきます。
① 利用者契約とは
就労継続支援B型事業は、障害者総合支援法(第29条)に基づく「利用契約制度」で運営されています。
つまり、事業所と利用者(またはその家族)は、サービス内容・利用日数・利用料などを文書で合意したうえで契約を結びます。
この契約を結ぶことによって、事業所は「サービス提供の責任を負う立場」となり、利用者は「サービスを受ける権利」を正式に得ることになります。
<行政書士の視点>
この契約は“形式的な書面”ではなく、事業所と利用者が信頼関係を築く出発点です。
どんなに小さな事業所でも、ここを丁寧に行うことでトラブルを防げます。
② 契約書の基本構成
就労継続支援B型の契約では、一般的に以下の3つが基本書類となります。
| 書類名 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 利用契約書 | サービス内容・期間・料金・解約条件などの約束 | 双方署名・押印が必須 |
| 重要事項説明書 | 事業所の運営方針・体制・苦情対応などの詳細説明 | 契約書とセットで交付 |
| 個人情報使用同意書 | 個人情報の利用目的・第三者提供に関する同意 | 別紙で同意を明確化 |
<行政書士の視点>
これらの書類は「セットで一式」として整備するのが原則です。
③ 利用契約のタイミング
契約は、受給者証が交付されたあとに結びます。
一般的な流れは次のとおりです。
1, 相談支援事業所によるアセスメント
2,市町村が支給決定(受給者証の交付)
3, 事業所で契約手続き・重要事項説明
4,支援計画(個別支援計画)の作成
5, サービス開始
<行政書士の視点>
“体験利用”を受け入れる場合も、「体験同意書」「個人情報同意書」などの簡易契約書類を交わしておくと安全です。
④ 契約の法的性質
利用契約は、民法上の「準委任契約」に近い性質を持ちます。
つまり、事業所がサービスを提供し、その対価として国(給付費)や本人(利用料)が支払う関係です。
| 契約当事者 | 役割 |
|---|---|
| 事業所 | 支援サービスを提供する義務を負う |
| 利用者 | 契約内容に基づいて通所し、利用料を支払う |
| 行政(市町村) | 支給決定・給付費の支払いを行う |
<行政書士の視点>
行政は契約の“監督者”ではありますが、契約の当事者ではありません。
あくまで、契約の主体は「事業所」と「利用者」です。
⑤ 契約時に説明すべき3つの基本事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ① サービス内容 | どんな支援・作業を行うのかを具体的に説明する |
| ② 利用料・工賃 | 利用料(1割負担)と工賃(支援結果)を区別して説明 |
| ③ 苦情・退所 | 苦情窓口、退所手続き、解約条件を明確に伝える |
「契約書に書いてあるから説明不要」ではありません。
法的には、“利用者が理解し同意した”ことを説明責任で証明できる必要があります。
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(開設後<運営スタート期>に関して)②>契約前に確認すべきこと<~行政書士が解説~>

