<就労継続支援B型事業所(再構築・発展編)⑦>多機能型転換の手続きとスケジュール<~行政書士が解説~>
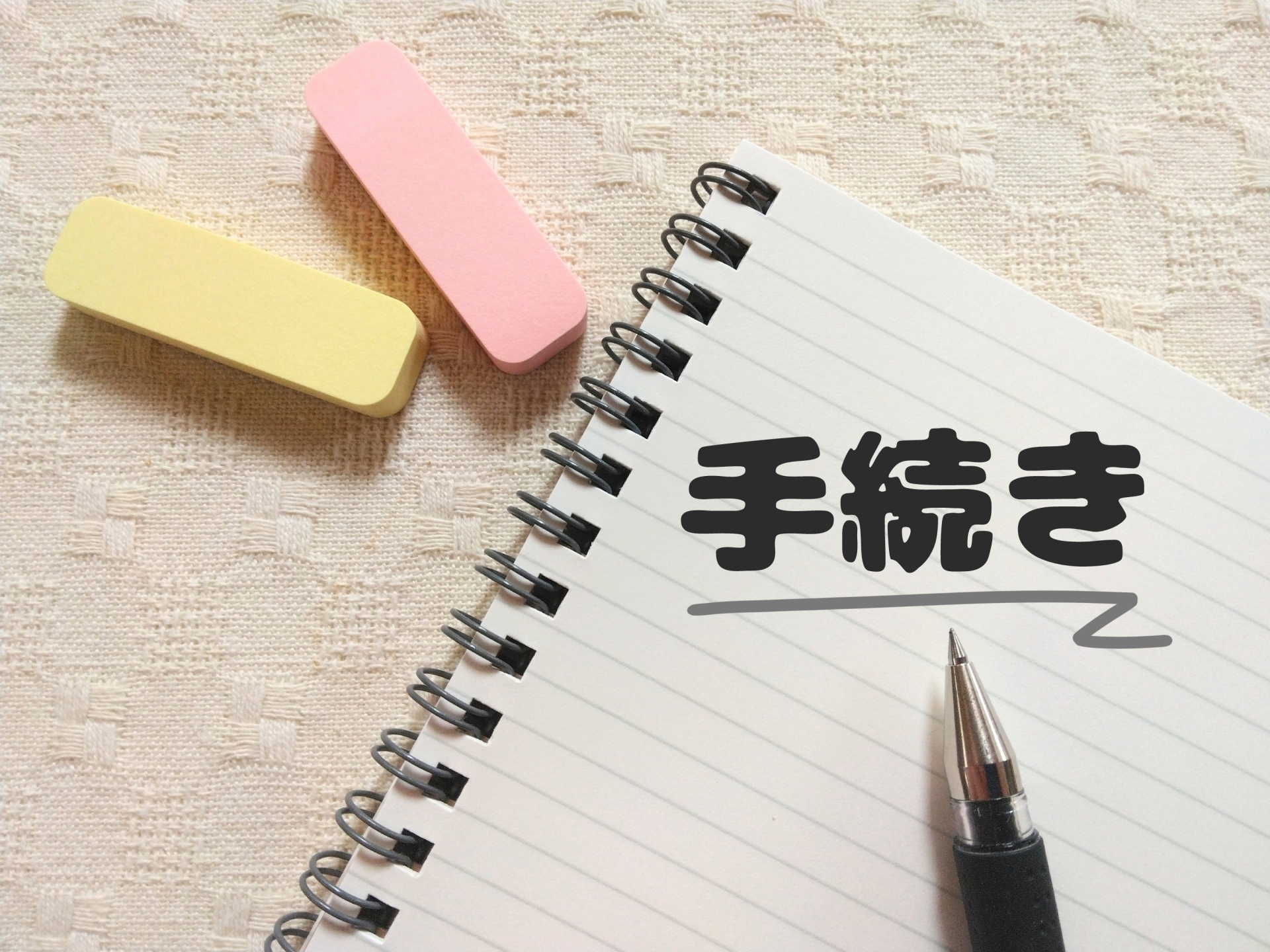
こんにちは、行政書士の大場です。
「多機能型への転換」と聞くと、「新しい事業をもう一つ立ち上げる」イメージを持たれる方も多いかもしれません。
しかし実際は、既存のB型事業の“指定変更”という手続きで行われます。
今回は、その手続きの流れと行政協議のポイントを整理します。
① 多機能型転換の基本構造
多機能型事業所は、複数のサービスを一体運営する仕組みです。
したがって、新しく事業を「追加する」のではなく、既存の指定(B型)の中に新しいサービスを組み込む形になります。
例)就労継続支援B型事業所 → 「就労継続支援B型・生活介護」の多機能型へ変更
という3ステップが必要です。
< 行政書士の視点>
多機能型は“新設”ではなく、“拡張”です。「新規指定+変更申請」が同時に進むため、行政協議の段取りが重要です。
② 手続きの全体フロー
以下は、宮城県内で一般的に行われている流れの例です。
| 段階 | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| ① 事前相談 | 県・市町村と構想段階で協議 | 開設の約2か月前まで |
| ② 書類作成 | 申請書・運営規程・体制届・平面図など | 約3〜4週間 |
| ③ 行政審査 | 県または指定都市が内容を確認・補正 | 約2〜3週間 |
| ④ 指定通知 | 指定書が交付される | 原則:開設の10日前まで |
| ⑤ 開設・運営開始 | 変更後の体制で運営開始 | 指定日以降 |
<注意点>
宮城県では、「開設予定日の2か月前までに相談」が原則です。
書類の不備があると、開設予定日を延期せざるを得ないケースもあります。
③ 提出書類一覧
| 書類名 | 内容・留意点 |
|---|---|
| 指定申請書(新規追加分) | 新たに追加するサービス内容を記載 |
| 指定変更届(既存B型) | 既存事業の「種別変更」として提出 |
| 運営規程(共通版) | サービス区分ごとの記載を一体化(共通部分を明記) |
| 体制届 | 職員配置・兼務・勤務時間を明記 |
| 管理者兼務届 | 共通管理者の場合に必須 |
| 平面図・配置図 | 共用設備・部屋の用途を明確に表示 |
| 利用者説明文書 | サービス内容変更の案内・同意書(既利用者用) |
| 誓約書・誓約事項 | 新規追加分の遵守事項確認書 |
④ 運営規程の整備ポイント
多機能型では、「複数のサービスを一つの規程で管理」する必要があります。
そのため、共通部分と個別部分を整理して記載します。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 共通部分 | 事業の目的・運営方針・職員体制・利用者の権利擁護など |
| 個別部分 | 提供するサービス内容・対象者・定員・支援時間・加算体制 |
⑤ 行政協議で確認される主な項目
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 建物・設備 | サービスごとの部屋分け、トイレ・動線の共用範囲 |
| 職員体制 | 管理者・サビ管・支援員の兼務状況 |
| 記録・台帳 | サービスごとの日報様式・工賃・勤務表管理 |
| 安全管理 | 消防法・避難経路・防災計画 |
| 運営規程 | 一体運営が明文化されているか |
<注意点>
「一体運営であること」を示すため、管理者・職員・記録様式・勤務表などを共通化している証拠資料を添付するとスムーズです。
⑥ スケジュール作成のコツ
多機能型転換では、複数手続きを同時進行させる必要があります。
進め方の例(目安:3か月前から)
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(再構築・発展に関すること)⑧>運営のポイント <~行政書士が解説~>

