<就労継続支援B型事業所(再構築・発展編)⑤>多機能型とは何か? <~行政書士が解説~>
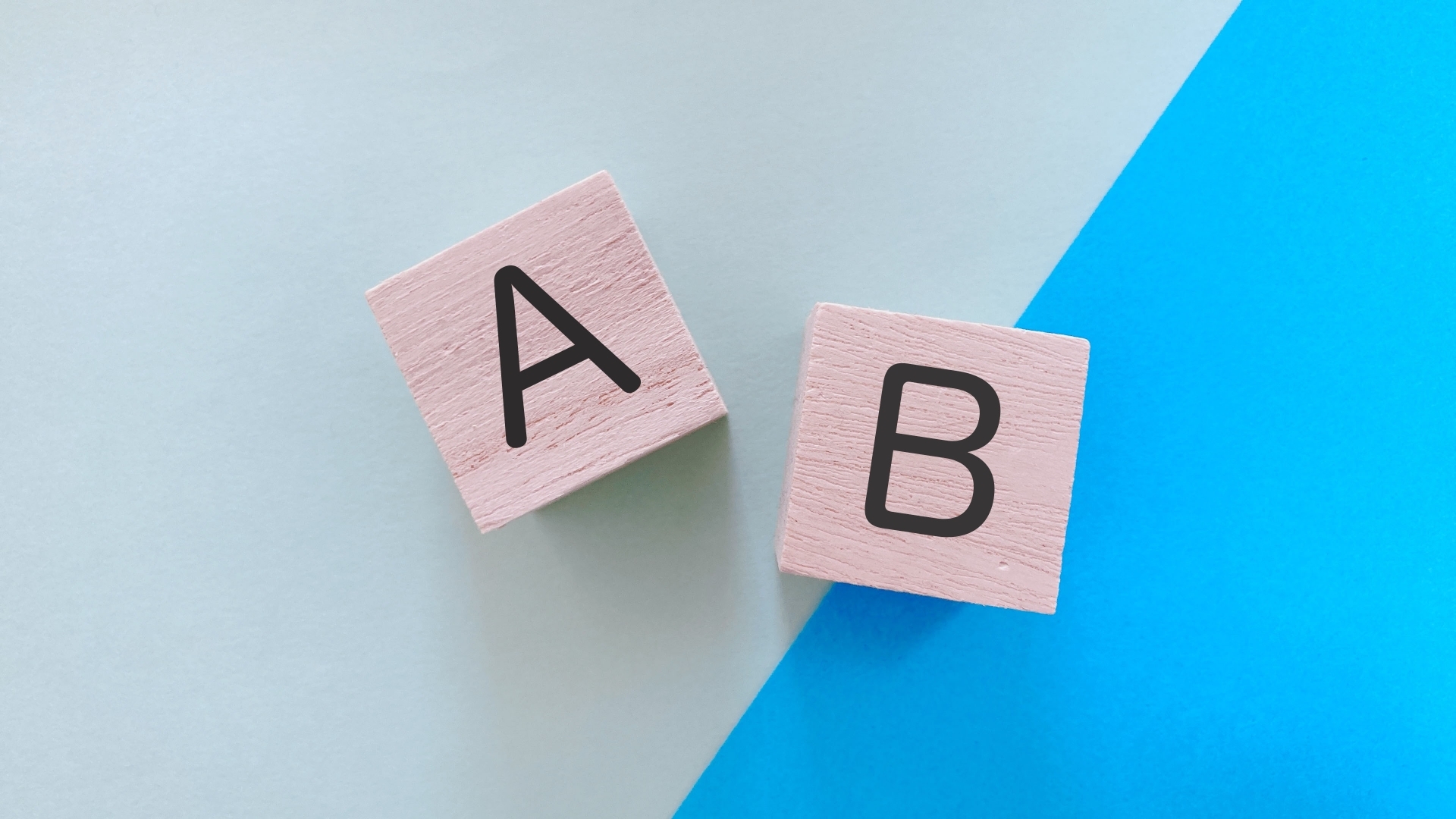
こんにちは、行政書士の大場です。
近年、全国的に「B型事業所の多機能型転換」が進んでいます。
ニュースや研修会などでも、「A型や生活介護との一体運営」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
それでも現場では、「多機能型って、結局どういう仕組みなの?」「B型事業所でもできるの?」
といった声が多く、制度の全体像がわかりにくい部分もあります。
今回は、就労継続支援B型の“新しいかたち”として注目される「多機能型事業所」について、制度の基本と位置づけを整理していきます。
多機能型とは?
「多機能型事業所」とは、複数の障害福祉サービスを一体的に運営できる形態のことをいいます。
といったように、一つの法人・一つの建物で複数のサービスを提供できる仕組みです。
厚生労働省では、この仕組みを「多様な就労ニーズに応えるための柔軟な運営形態」として位置づけています。
なぜ多機能型という仕組みがあるのか
就労支援の現場では、利用者の特性や体調により「A型は難しいけれど、B型なら通える」「午前中だけ生活介護を利用して、午後は軽作業をしたい」といった“個別化ニーズ”が年々増えています。
そのため、法人が複数の事業を運営し、一つの場所で継続的な支援を行えるようにしたのが「多機能型事業所」です。
<行政書士の視点>
多機能型は「別々の指定をまとめる」のではなく、一体的な運営を前提とした“包括的指定”です。
そのため、一つの管理者・一つの運営規程で複数サービスを行うことが可能になります。
多機能型と「併設型」の違い
| 区分 | 多機能型 | 併設型 |
|---|---|---|
| 仕組み | 複数サービスを一体的に運営(1つの指定) | 各サービスが独立して運営(別指定) |
| 管理者 | 共通管理者でも可 | 各事業所に管理者が必要 |
| 運営規程 | 共通規程で一体運営 | 事業ごとに別規程 |
| 実地指導 | 一体で実施 | それぞれ独立に実施 |
| メリット | 職員・設備の共有がしやすい | 管理の柔軟性が高い |
| デメリット | 一体運営を説明できないと指摘を受ける | コスト・人員が重複しやす |
多機能型にできる組み合わせ例
| パターン | 内容 | 主なねらい |
|---|---|---|
| A型+B型 | 一般就労移行を目指すステップアップ型 | 支援の継続性を確保 |
| B型+生活介護 | 重度障がい者の体調や希望に応じて柔軟対応 | 利用者の選択肢を広げる |
| 就労移行+B型 | 訓練と就労体験を同時に提供 | 就労準備支援の充実 |
<行政書士の視点>
特に「B型+生活介護」は宮城県でも増加傾向です。
午前は生活介護で体調を整え、午後はB型で軽作業を行う・・そんな利用者の生活に寄り添う運営形態が求められています。
B型事業にとってのメリット
→ 就労意欲や障がい特性に合わせた柔軟な支援が可能に。
→ サービス構成を分散できるため、報酬改定や定員変動の影響を受けにくくなる。
→ 生活支援・就労支援を一体で行うことで、行政・医療・家族との連携が強化される。
多機能型転換に向けての最初の一歩
<行政書士の視点>
転換は「新しい指定申請」と「既存B型の指定変更」が同時に進みます。行政との事前協議が最も重要なステップです。
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(再構築・発展に関すること)⑥>なぜ今“多機能型”なのか? <~行政書士が解説~>

