<就労継続支援B型事業所を運営されている法人様向け デジタル印刷事業導入支援②>持続的な生産活動をつくる
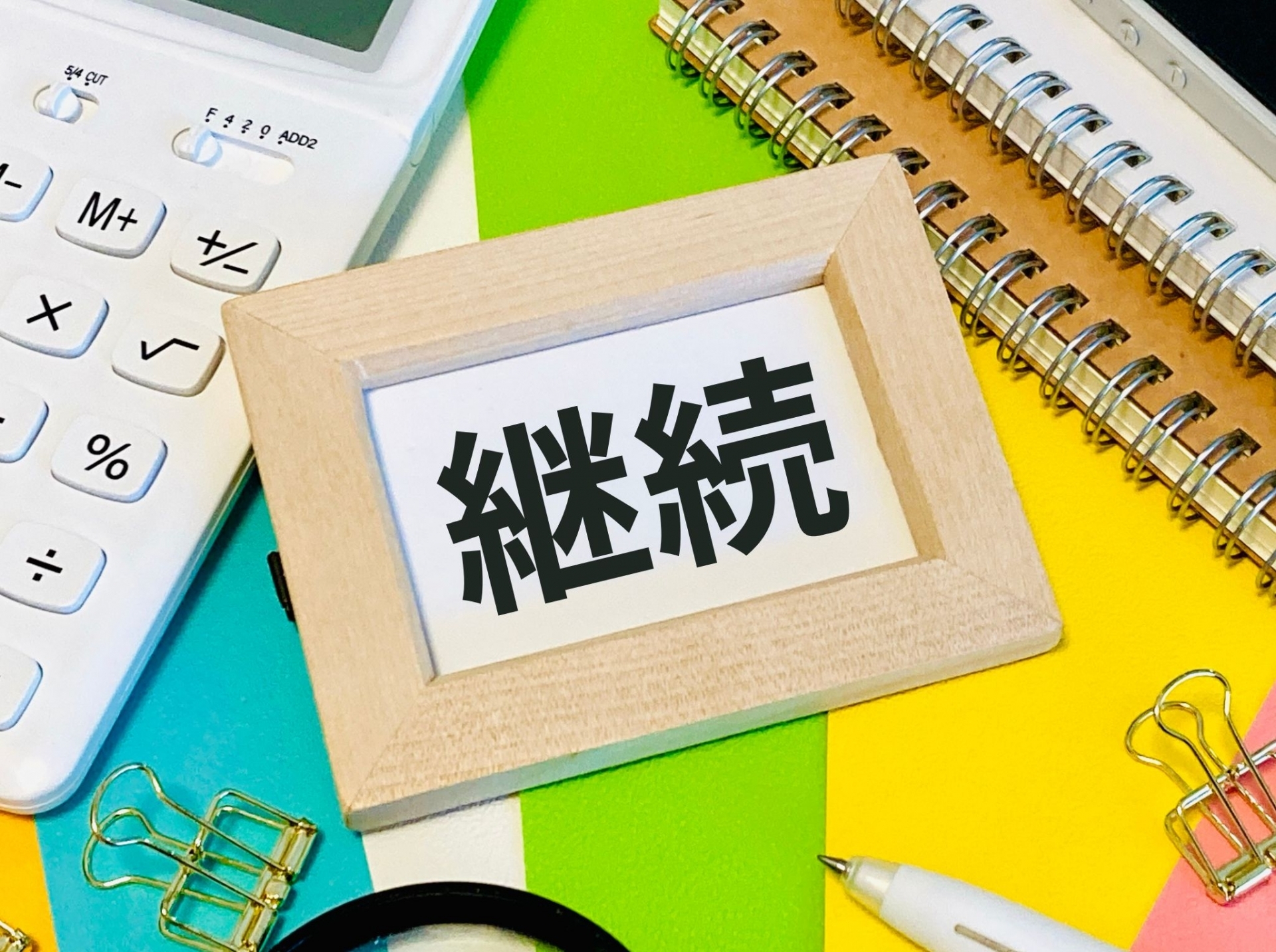
こんにち、行政書士の大場です。
B型事業所の生産活動って、始めるより“続ける”ほうがずっと難しいです。
「最初はうまくいったけど、3か月で止まった」「材料費のほうが高くついた」そんな声、現場で本当によく聞きます。
では、どうすれば“続く仕事”になるのか?
その答えのひとつが、デジタル印刷事業の導入です。
1. 始めるのは簡単じゃない。でも、仕組みにすれば続く
「印刷機を買って置けば仕事になる」そう思われがちですが、実際には、営業・工程管理・品質チェック・支援体制、全部そろって初めて“事業”になります。
でも逆に言えば、その仕組みさえ整えれば、小さく始めて大きく育てられる現実的なモデルなんです。
2、B型事業所と相性がいい理由
印刷の仕事には、いくつもの工程があります。
印刷 → カット → 折り → 検品 → 封入 → 納品。この分担の多さが、B型事業所に向いています。
得意な作業を任せたり、支援員がフォローしたり、「みんなでひとつのものを完成させる」チームワークが生まれます。
文字の大きさ、色のコントラスト、やさしい言葉づかいなど
これらは、福祉を理解している人でなければ気づけません。
お客様も同じ福祉業界だから、共感でつながります。
3. 続けるほど広がる、“紹介とリピート”の連鎖
名刺、封筒、パンフレット・行事案内・お知らせ通信など、毎月発行されるものが中心です。
「うちの施設もお願いしたい」という紹介が自然に生まれます。
信頼がそのまま受注につながり、他の作業にはない強みになります。
4. 「社会性」が事業の付加価値になる
LIMEX<ライメックス>などの環境素材型の用紙を使えば、“福祉×環境”という新しい価値が生まれます。
地域企業のCSR活動<企業の社会的責任>や自治体連携にも広げやすく、「社会にいい事業」として胸を張れるのがこの分野です。
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所を運営されている法人向け 生産活動の拡充と工賃アップ戦略③>営業先は“福祉の中にある”

