<障害者優先調達推進法とは①>「障害者優先調達推進法」とは何か?
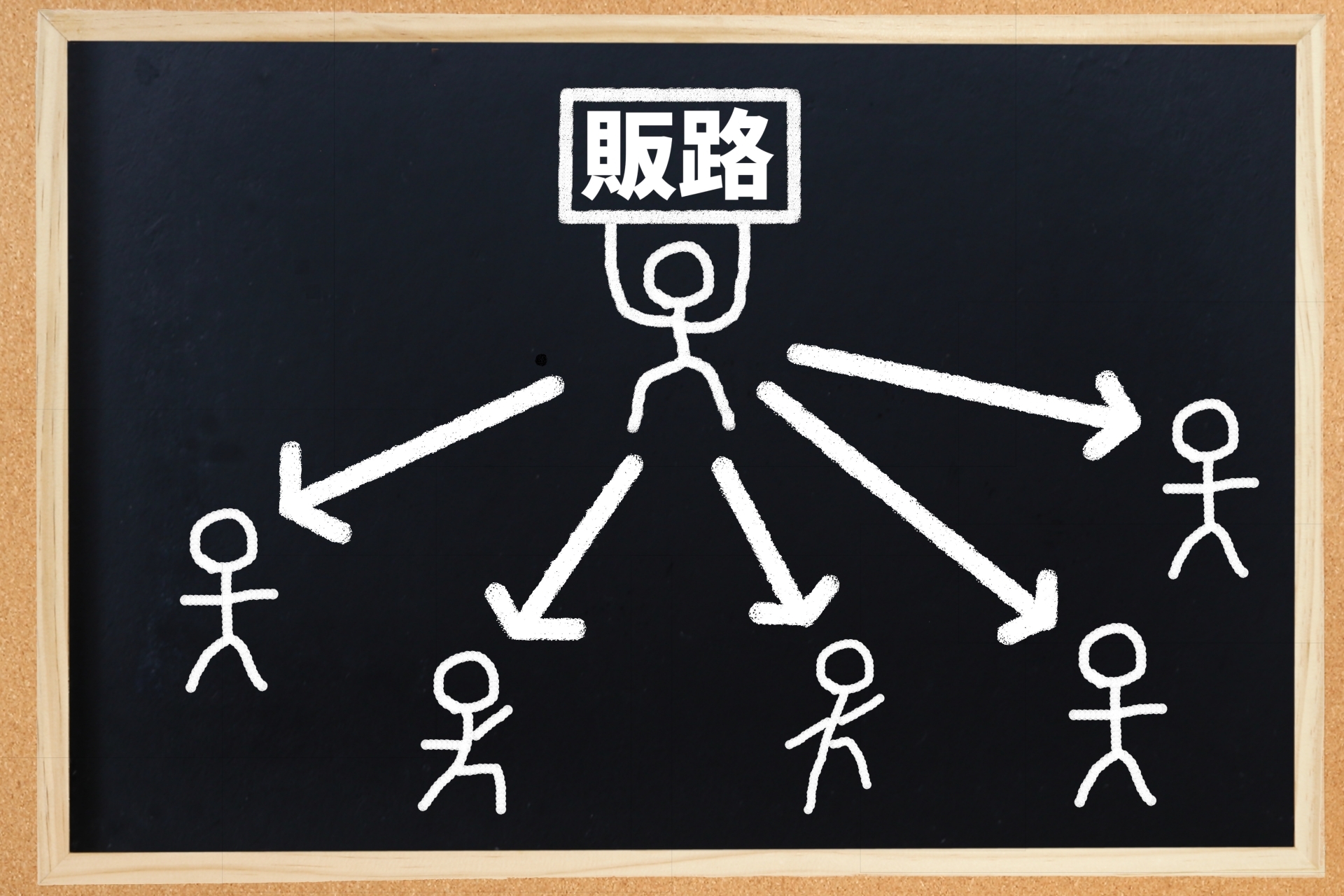
こんにちは、行政書士の大場です。
今日は「障害者優先調達推進法」という、少し堅い名前の法律をテーマにしてみます。
名前だけ聞くと難しそうですが、実は、B型事業所や福祉事業者にとって、「販路を広げるチャンス」になる法律なんです。
制定の背景:「働く場」を“つくる”ために
この法律の正式名称は、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」平成25年(2013年)に施行されました。
目的は明確です。
国や自治体などの公的機関が、できるだけ障害者就労施設等から物品やサービスを“優先的に購入”するようにする。
つまり・・・
「買って応援」ではなく、“仕事を発注することで支える”という考え方です。
これは単なる福祉政策ではなく、障害者の「働く力」を経済活動の中で評価する仕組みでもあります。
公共調達という「販路」
・広報誌の印刷
こうした仕事を、国や自治体は毎年、数多く外注しています。
その発注先を、「一般企業だけでなく、障害者就労施設にも広げよう」というのがこの法律の狙いです。
実績は「自治体ごと」に公表される
法律に基づき、各省庁・自治体は毎年「調達実績報告書」を作成・公表しています。
たとえば宮城県のホームページを見ると、「令和5年度 障害者就労施設等からの物品等の調達実績」が掲載されています。
法律の意義:助成金ではなく“市場を作る”仕組み
これは、工賃アップや自立支援の土台になります。
行政書士としての視点
これらは行政書士が支援できる重要な部分です。
“買ってもらえる事業所”になるために、法的・実務的な整備は欠かせません。
次回のブログはコチラ⇒<障害者優先調達推進法とは②>調達の仕組みと対象となる取引

