<就労継続支援B型事業所(独立編)③>法人をつくる前に知っておきたい制度の話<~行政書士が解説~>
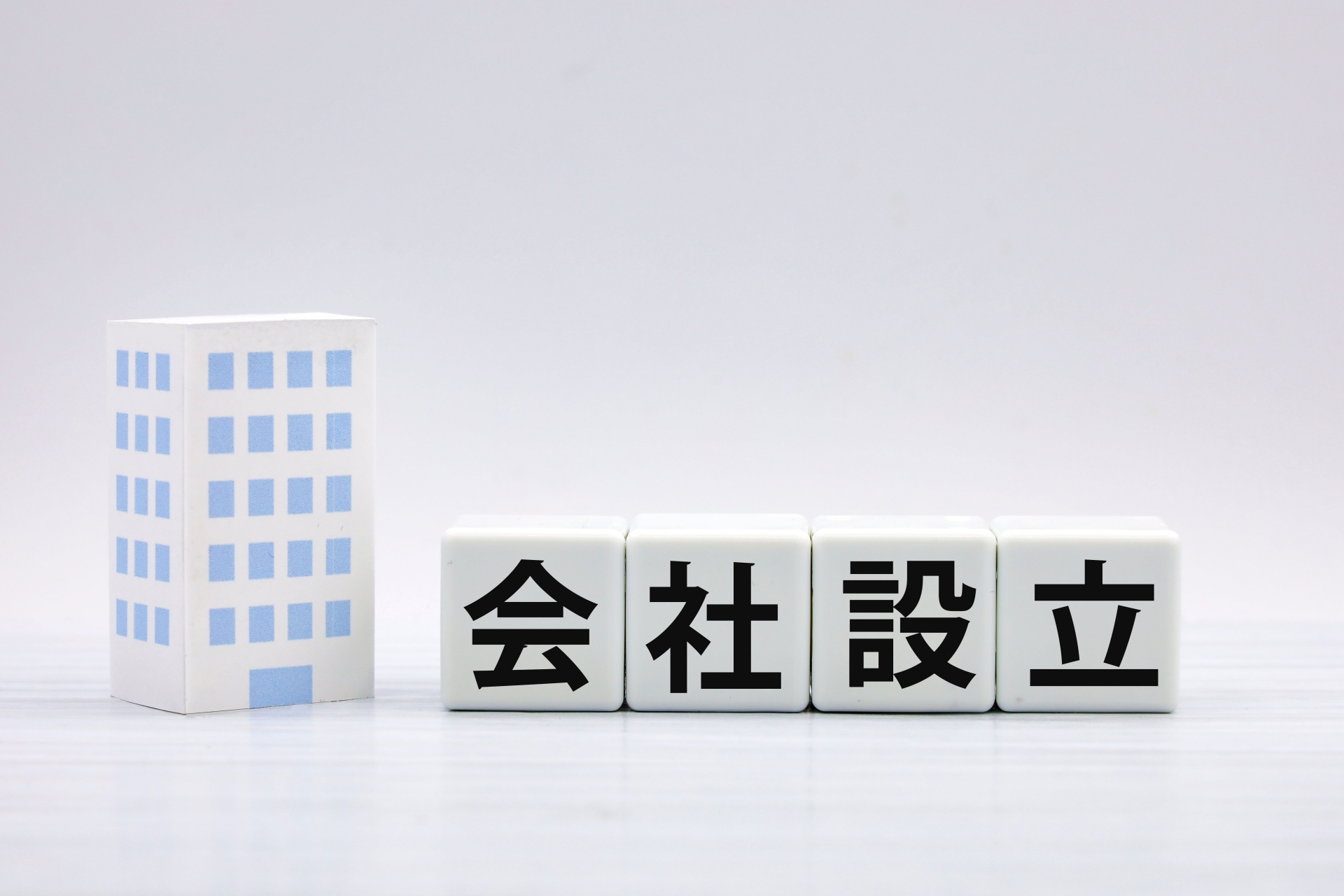
こんにちは、行政書士の大場です。
B型事業所を立ち上げるとき、考えるのが「法人の形態をどうするか」です。
“株式会社でいいのか?” “NPOのほうが認可されやすいのか?”実は、ここでつまずく方がとても多いです。
でも、焦らなくて大丈夫です。
大事なのは、「どんな理念を形にしたいか」に合わせて選ぶことです。
B型事業所は「法人格」が必須
就労継続支援B型事業は、個人では運営できません。
必ず法人として指定を受ける必要があります。
法人の形は、主に次の4つです。
| 法人の種類 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 株式会社 | 設立が早く、資金調達の自由度が高い | 事業性を重視、複数事業を展開したい場合 |
| 合同会社 | 小規模・低コスト、意思決定が柔軟 | 少人数で始めたい独立型 |
| 一般社団法人 | 非営利型、公共性を重視 | 地域連携・福祉的活動中心 |
| NPO法人 | 審査期間が長いが社会的信用が高い | 寄付・ボランティア基盤を持つ場合 |
どれが“正解”というわけではなく、「理念に合わせた法人選び」が重要です。
「目的」と「持続性」で選ぶ
たとえば、「利用者さんと一緒に地域とつながる印刷事業をやりたい」、「農業やデザインなど複数のしごとを展開したい」こうした“事業型の理念”であれば、株式会社や合同会社のように機動的な法人が向いています。
一方で、「地域の居場所をつくりたい」「公共的な連携を進めたい」場合は、一般社団法人やNPO法人のほうが適しています。
ただし、どちらを選んでも、障害福祉事業としての指定を受ければ制度上の扱いは同じです。
違うのは、理念と運営の自由度のバランスです。
違うのは、理念と運営の自由度のバランスです。
定款と目的の書き方がカギ
法人設立のときに作る「定款」には、事業の目的(=どんな活動をする法人か)を明記します。
ここで「障害福祉サービス事業」とだけ書くのではなく、
・地域との連携を通じた就労支援事業
・印刷・デザイン・販売促進支援に関する業務
・福祉的就労の支援および関連事業
・地域との連携を通じた就労支援事業
・印刷・デザイン・販売促進支援に関する業務
・福祉的就労の支援および関連事業
のように、将来展開したい方向も入れておくと安心です。
後から生産活動や多機能化を追加するときに、「定款変更」が不要になる場合があります。
定款は“将来の設計図”です。
今できることだけでなく、“これからやりたいこと”も書いておくとよいでしょう。
後から生産活動や多機能化を追加するときに、「定款変更」が不要になる場合があります。
定款は“将来の設計図”です。
今できることだけでなく、“これからやりたいこと”も書いておくとよいでしょう。
行政手続きの流れ
法人をつくっただけでは事業は始められません。
次のような手続きが必要です。
次のような手続きが必要です。
1 法人設立(登記完了)
2 県・市町村との事前協議
3 建物調査・消防確認
4 指定申請書類提出
5 審査・指定通知
2 県・市町村との事前協議
3 建物調査・消防確認
4 指定申請書類提出
5 審査・指定通知
この流れをあらかじめ理解しておくと、スケジュールの見通しが立ち、融資申請や建物契約もスムーズです。
次回のブログはコチラ⇒
次回のブログはコチラ⇒
2025年11月06日 02:50

