<物件選定>⑮用途変更が必要な物件・不要な物件
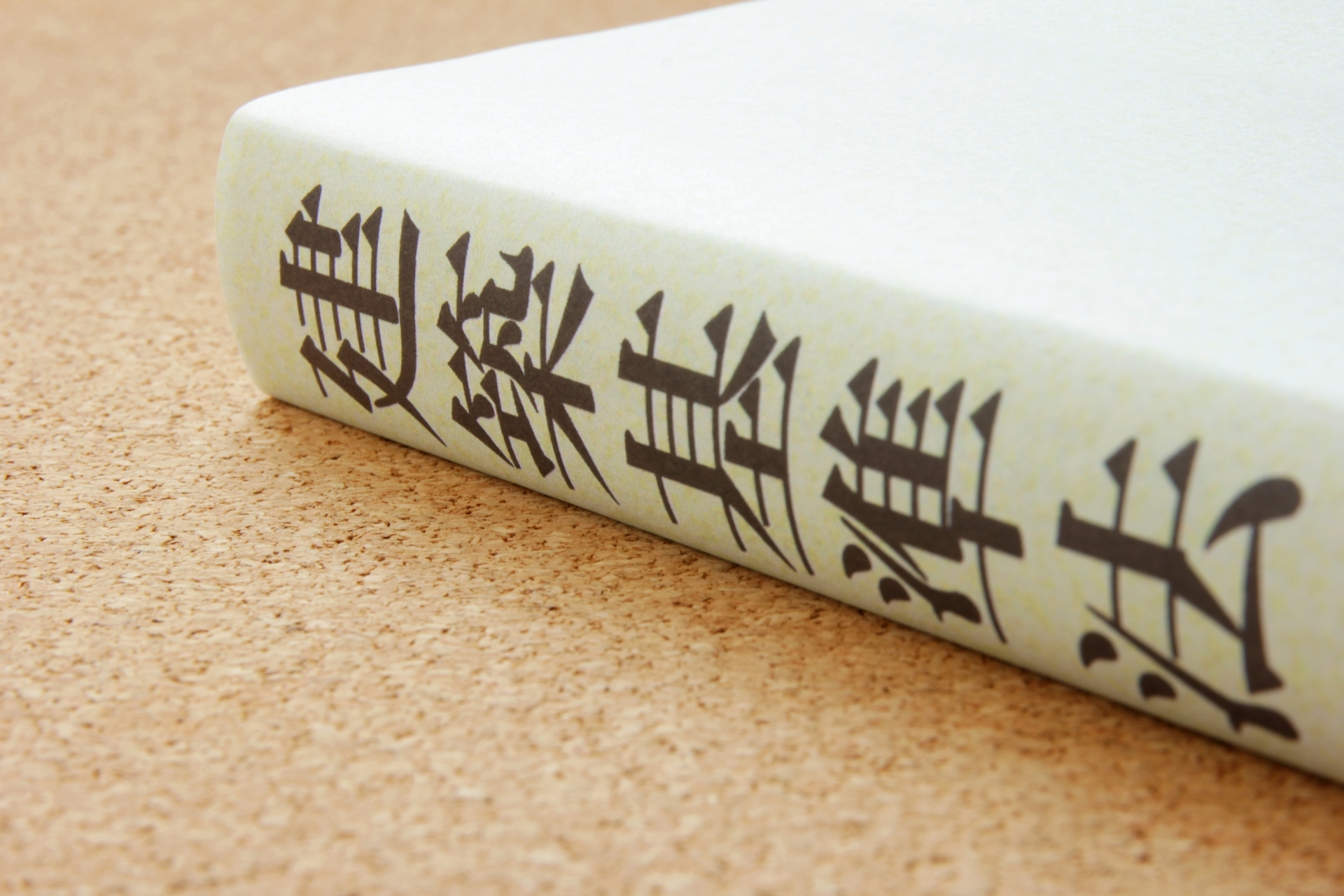
こんにちは、行政書士の大場です。
B型事業所の物件を選ぶ際、最初の判断ポイントになるのが 建物の用途 です。同じように見える物件でも、用途が違えば使える・使えないが大きく分かれます。今回は、B型事業所として利用する際に用途変更が必要な物件と、不要な物件の違い を整理していきます。
1. 基本原則:用途変更とは何か?
建築基準法では、建物は「用途(使ってよい目的)」が決められています。
例えば
・事務所
・店舗
・住宅
・工場
・病院
・福祉施設(通所)
B型事業所は、建築基準法上 “福祉施設(通所系)” に該当する可能性が高い用途 として扱われます。
つまり…
元の用途と、B型事業所としての用途が違う場合、用途変更が必要になる可能性があるということです。
ただし、“必ず必要” なわけではなく、建物の構造や面積により 「軽微変更」扱いで済む場合」 もあります。
2. 用途変更が必要な可能性が高い物件
ここに該当する物件は、 ほぼ用途変更の対象 になります。
① 住宅(木造戸建・アパート・マンションの1階含む)
・元用途:住居
・福祉用途との隔たりが大きい
・避難経路・防火区画も不足
※仙台市では「住宅→通所福祉」は最も難易度が高いです。
② 店舗・飲食店跡
・消防設備が不足
・誘導灯・火災報知器が未整備
・排煙設備の規定を満たさない
※飲食店は特に厳しい。
③ 木造の古い建物(検査済証がない)
・元用途を証明できず、建築指導課が判断できない
→ 用途変更不可扱い になりやすい。
→ 用途変更不可扱い になりやすい。
④ 2階以上のテナントで避難経路が1つしかない
・通所施設は避難ルートの確保が重要
⑤ 床面積が大きく、収容人数が増える物件
-
収容人数が増えるほど消防設備が高度化
→ 工事費が膨らむ可能性大
3. 用途変更が不要になる可能性が高い物件
B型事業所に用途にしやすい物件 です。
① 福祉施設の居抜き
・すでに福祉用途で建てられている
・大きな工事なしで使えることが多い
→ 最も安全でコストが少ない
→ 最も安全でコストが少ない
② クリニックなど医療系テナント
・防火・避難基準が高い
・通所系福祉施設へ転用しやすい
③ 鉄骨造・鉄筋コンクリート造のテナントビル
・用途変更の柔軟性が高い
・非木造は基準に強い
④ 平屋の広い物件
・避難が容易
・用途区分の変更も行いやすい
⑤ 元々「事務所用途」で消防設備が整っている物件
・一定の範囲では用途変更不要の可能性も
(※行政判断による)
(※行政判断による)
4. 最終判断は“建築指導課+消防署”で決まる
仙台市では、
B型事業所の開所支援において
「物件契約前の建築・消防の事前協議」が実質必須です。
< 必要資料>
・平面図(寸法入り)
・元用途(建築確認資料)
・構造(S造・RC造など)
・想定利用定員
・想定利用定員
・職員数(収容人数)
・生産活動の内容
2025年11月21日 22:47

