<就労継続支援B型事業所 加算の考え方②>加算には2種類あり “体制系加算”とは
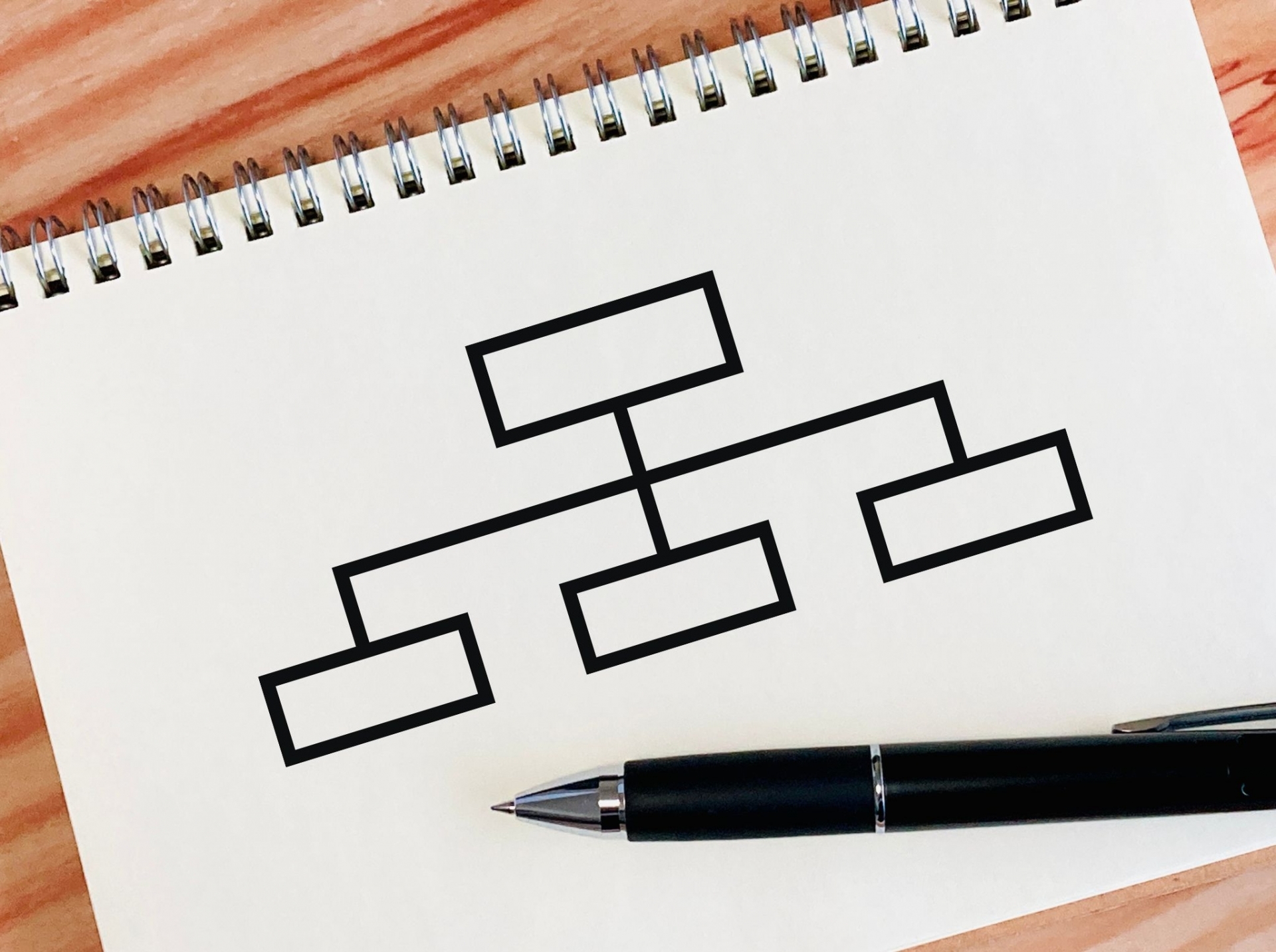
こんにちは、行政書士の大場です。
前回(第1回)は、「加算とは何か?」をお話ししました。
前回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所 加算の考え方①>そもそも「加算」とは何か?
① 体制系加算(支援の土台)
② 生産活動系加算(工賃を上げる)
この順番で積み上げないと、加算は取れません。
加算には2種類ある
加算は本質的に次の2つです。
…支援の仕組み・職員配置・訓練体系などの“土台”を評価
2)生産活動系加算
…働く・生産・工賃アップの“実際の取組”を評価
B型事業所で加算を取れない典型的パターンは、「生産活動系をいきなり狙って、体制系が整っていない」です。
国も自治体も、体制系が整っていなければ、生産活動系加算は“実効性がない”と判断します。
まず“体制系加算”が必要な理由
体制系加算は、言い換えると「支援の準備が整っているか?」、「加算を受け取る土台があるか?」を評価する加算です。
・工程改善を説明できず
・記録の裏付けが弱く
・生産活動系加算は取れません
では具体的に、体制系加算の中身を見ていきます。
体制系加算とは?
B型事業所で重要な体制系加算はこの5つ
1)訓練等支援体制加算(最重要)
2)サービス提供体制加算(職員配置の評価)
3)医療連携体制加算
4)福祉・就労連携加算
5)生活支援(口腔・栄養)系加算
ここからは、それぞれを“具体的に”解説します。
1)訓練等支援体制加算(B型事業所で最優先)
「訓練の体系が整理され、段階的な支援ができる事業所」を評価する加算です。
現場では最も実用性が高く、監査でも確実にチェックされる“核となる加算”です。
(必要な具体的要件)
(1)訓練体系が段階的に作られている
・初級→中級→上級のステップ
・“生活訓練”と“職業訓練”が混ざらないように構成
・認知特性に応じた訓練項目が整理されている
→ 1枚の「訓練体系表」で説明できることが重要
(2)訓練マニュアル(手順書)がある
・訓練内容
・方法
・手順
・注意点
・到達目標
→ 「誰が見ても同じ訓練ができる状態」が必要
(3)個別支援計画と訓練が連動
・個別支援計画内に“訓練目標”を明記
・その訓練が訓練体系のどのレベルか示せる
・訓練とモニタリングのセット運用
(4)訓練記録が残っている
・日々の振り返り
・ステップの進捗
・達成・未達成の理由
→ 記録の有無が算定の生死を分けます(返還リスク最大ポイント)
(5)月1回以上の支援会議
・職員全員で情報共有
・訓練の方向性を確認
・議事録が残っている必要あり
これらが揃うと、訓練等支援体制加算は非常に取りやすくなります。
2)サービス提供体制加算
内容を簡単に言えば、「経験のある職員や研修を受けた職員がいる」ことを評価する加算
・研修修了者(強度行動障害支援者研修など)がいるか
・サビ管の経験年数と研修状況
→ 要件は自治体ごとに微妙に差があるため確認が必須
3)医療連携体制加算
医療的ケアが必要な利用者が多い事業所や、精神疾患で服薬調整が必要なケースがある事業所で重要。
・急変時の対応マニュアル
・発作・てんかんへの対応手順
・医療情報の共有(記録・職員間の連携)
→ 「医療が必要な利用者でも安心して通える」体制が整っていること
4)福祉・就労連携加算(自治体差が大きい)
就労移行支援・就労定着支援との協力体制を評価。
・支援会議の共同開催
・情報共有の仕組み(記録が残る形式)
・就労準備性の評価ツールの活用
→ “連携している証拠”を残すことが最重要
5)生活支援(口腔・栄養等)系の加算
利用者に高齢者や身体疾患が多い事業所の場合、この加算が取れる可能性があります。
・食支援(ミールラウンド等)
・口腔衛生の支援
・個別支援計画への反映
・衛生管理マニュアル
→ 生活支援に力を入れている事業所向け
体制系加算が取れる事業所の共通点
・個別支援計画の質が高い
・記録が丁寧で、量ではなく“質”を意識している
・マニュアルが整理されている
・会議が形骸化せず、議事録がある
・職員の役割分担が明確
→ これらが揃っていると、加算は自然と取れる体制になります。
1)訓練体系
2)訓練マニュアル
3)個別支援計画と訓練の連動
4)記録
5)会議体の運営
この5つです。
次回のブログはコチラ⇒

