<就労継続支援B型事業所向け 生産活動導入サポート「デジタル印刷事業編」①>なぜ今、“デジタル印刷事業”なのか<行政書士が解説>
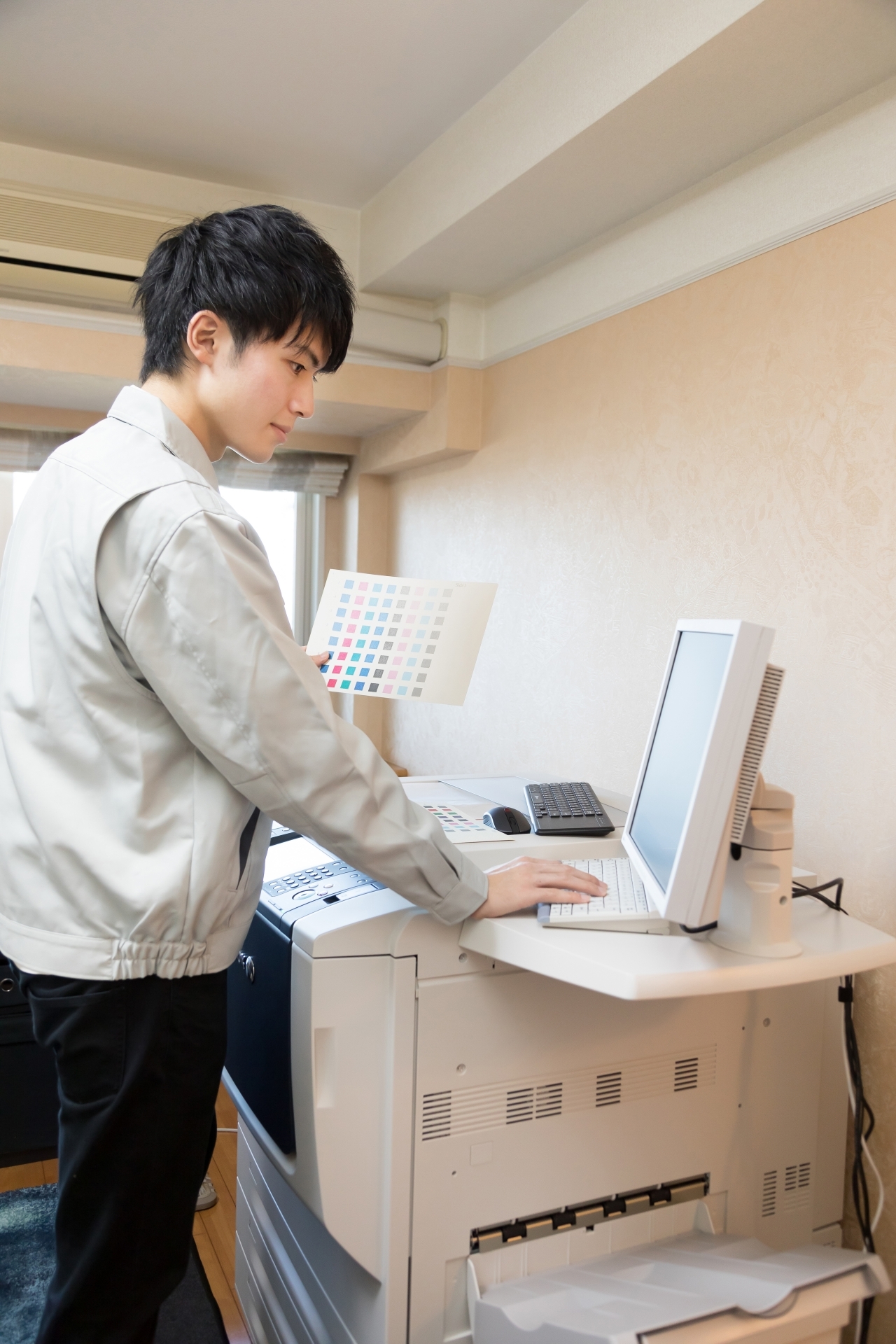
こんにちは、行政書士の大場です。
本日からブログシリーズとして30回にわたり、<就労継続支援B型事業所向け 生産活動導入サポート「デジタル印刷事業編>をお伝えしていきます。本日は第1回目になります。
それでは始めます。
就労継続支援B型事業所の現場では、「次の生産活動をどう作るか」が重要なテーマになっています。
令和6年度の報酬改定でも「工賃向上」や「生産活動の多様化」が明確に位置づけられ、各自治体でも“工賃アップ計画”の提出や実績管理が求められるようになりました。
つまり、制度そのものが「新しい生産活動を模索する時代」に入っています。
“今の仕組みのままでは上がらない”
厚生労働省の最新調査によると、全国のB型事業所の平均工賃は月17,295円、10年前と比べてもほとんど上昇していません。
背景には、こんな構造的な課題があります。
つまり、「努力しても上がりにくい仕組み」が根底にあるのです。
デジタル印刷は“構造を変える”選択肢
こうした現状の中で注目され始めているのが、デジタル印刷事業です。
まだ導入事例は限られますが、障害福祉現場と地域企業の間をつなぐ「新しい生産活動」として検討が進んでいます。
なぜデジタル印刷なのか?理由はシンプルです。
行政手続きも“制度設計の一部”
導入後はチームで支える
導入後の運用・教育・営業・品質支援は、提携のブランディング会社(FBS株式会社)が担当します。
行政書士が制度を、FBS株式会社が現場を支えます。この「制度 × 運用」の両輪が、継続できる生産活動の仕組みをつくります。
デジタル印刷事業は、まだ始まったばかりの挑戦です。
しかしその仕組みは、“下請けから脱却し、地域と直接つながる”という流れに合致しています。
B型事業所が自ら仕事を生み出し、利用者の工賃を上げ、地域に貢献できる。
このブログシリーズでは、その仕組みと導入のステップを、制度と現場の両面から解説していきます。
次回は、第2回|“印刷”ではなく“つながる仕事”へ
デジタル印刷が障害福祉現場にもたらす“社会的な意味”を掘り下げます。
次回のブログはコチラ⇒<生産活動導入サポート「デジタル印刷事業編」②>印刷ではなくつながる仕事へ<行政書士が解説>
デジタル印刷事業の事業説明会&相談会のご予約はコチラ⇒予約フォーム

