制度・手続きの悩み②<指定基準の読み方がむずかしい!>
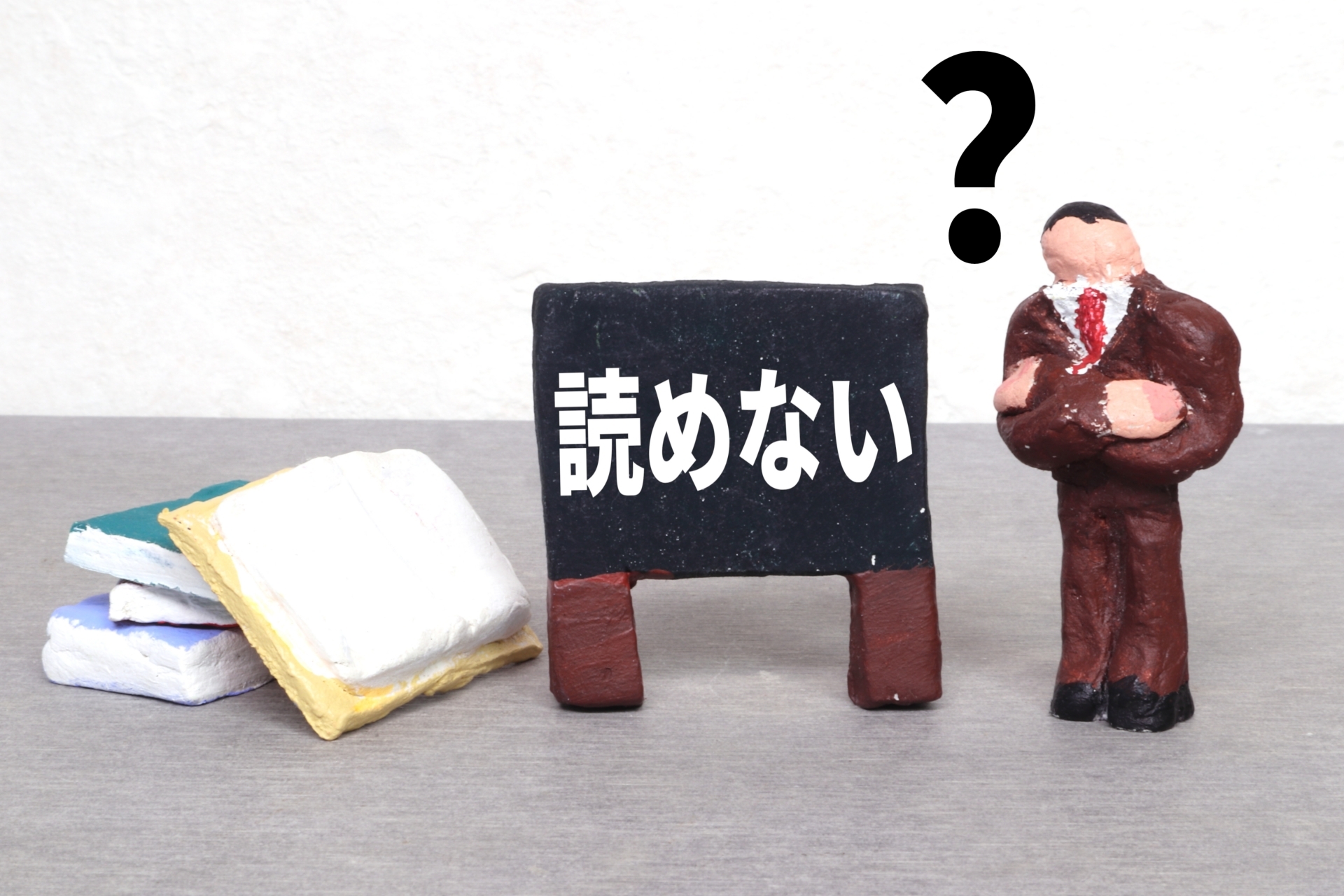
こんにちは。行政書士の大場です。
このブログシリーズでは、就労継続支援B型事業所の「よくある悩み」をひとつずつ取り上げて、専門用語をできるだけ使わずに、現場目線で分かりやすくお話します。
さて、今回のお悩みは
「指定基準の読み方が難しい!」「厚生労働省令を読んでも意味が分からない!」です。
まず、“厚労省令”って何?
「就労継続支援B型事業を行う者は、当該事業に係る従業者のうち、サービス管理責任者を置かなければならない」
つまり「サビ管置いてください」ってことです。それだけです。
読み方のコツ① “誰が何をする”を抜き出す
「指定就労継続支援B型事業者は、作業室、休憩室、相談室を設けるものとする」
これが読む気をなくす原因です。
読み方のコツ② “なぜそうなってるか”を考える
読み方のコツ③ “県の手引き”を見る
宮城県と岩手県では、同じ書類でも呼び方が違ったりします。
だから、ネットの情報をそのまま信じると混乱します。
読み方のコツ④ わからないときは“図にする”
「職員配置」=だれが何人必要?
を図にしてみると、頭にスッと入ります。
|
|
これだけで一気に見える化です。
文章より図のほうがわかりやすいんですよね。
大場のぼやき
正直、制度の文章はほんとに硬いです。
「もうちょっとやさしく書けないのかな」と毎回思います。
でも、だからこそ、現場の人が“分かる言葉に直す人”が必要なんだと思います。
行政書士の仕事って、書類を作ることよりも、こういう制度の翻訳をすることのほうが多いんです。
「つまりどういうこと?」って聞かれたら、
「こういうことです」って笑って返せる人でありたいですね。
次回のブログはコチラ⇒


